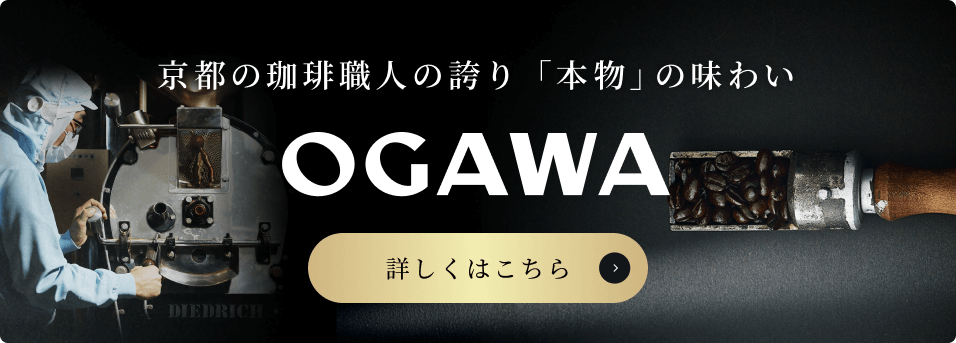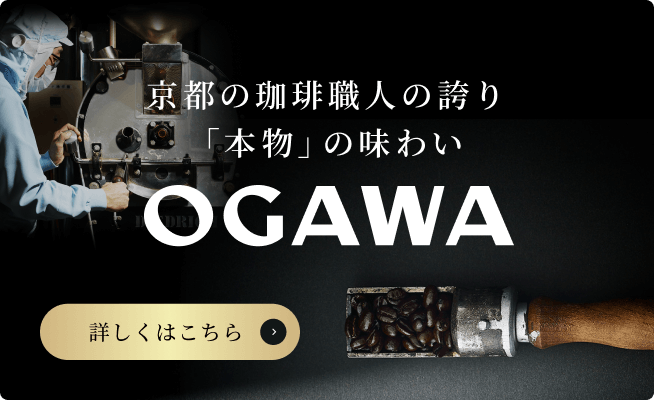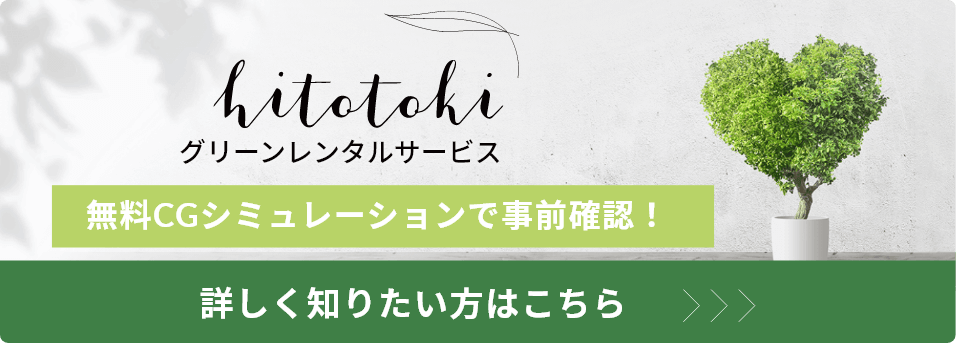従業員満足度(ES)は企業活動や業績に大きく影響する要素として近年ますます注目を集めています。従業員が自分の職場や働き方に満足しているかどうかは、離職率や生産性、さらに企業のブランドイメージにも直結します。そのため、多くの企業がESの向上を経営戦略の中心に据え、さまざまな取り組みを進めている状況です。
本記事では、まず従業員満足度の定義や重要性を整理したうえで、従業員満足度が高い企業にもたらされる具体的なメリットを解説します。さらに、実際の企業事例を交えながら、どのように施策を立案し、社員のモチベーションや定着率を高められるかを具体的に見ていきます。従業員満足度は一朝一夕で劇的に変わるものではありませんが、継続的な取り組みを行うことで企業の業績向上や人材確保につながる効果が期待できます。
最後に、施策を成功に導くポイントや今後の企業経営における展望まで含めて解説し、従業員満足度向上の全体像を理解できるようにまとめました。特に、柔軟な働き方や福利厚生の拡充、オフィス環境の改善は多くの企業ですでに成果を上げつつあります。ぜひこの記事をヒントに、自社の従業員満足度向上に取り組むきっかけにしてみてください。
従業員満足度(ES)とは?定義と重要性
まずは従業員満足度の基本的な概念を整理し、その重要性を確認していきましょう。
従業員満足度(Employee Satisfaction)とは、従業員が給与や働きがい、職場環境など企業に対してどの程度満足しているかを示す指標です。企業においては売上や利益と同様に重視すべき要因のひとつとされており、従業員満足度が高い環境ほど離職率の低下につながると指摘されています。また、この指標は企業文化や経営理念が従業員にどれだけ浸透しているかを知るうえでも重要な尺度です。
従業員満足度が高い組織では、社員同士のコミュニケーションが円滑で、新しいアイデアやイノベーションが生まれやすい土壌があります。たとえば、外国籍社員も含めて多様なバックグラウンドを持つ人材が働く企業では、多様性を取り込みやすい風土が育ち、スピード感ある変革を進められます。従業員満足度を高めることは、企業が柔軟かつ競争力のある経営を行うための基盤となるのです。
さらに、厚生労働省が推奨しているように、従業員満足度の向上は社会全体の生産性向上にも寄与するとされています。従業員が心身ともに健康な状態で働ける環境は、品質の高い顧客対応にもつながり、それが企業の競争力強化に直結します。これらの要素から、従業員満足度は企業経営の要ともいえる存在になっています。
出典:
(今後の雇用政策の実施に向けた現状分析に関する調査研究事業 報告書 ~企業の雇用管理の経営への効果~ 参照)
従業員満足度とエンゲージメントの違い

従業員満足度とエンゲージメントは似た概念ですが、明確な違いがあります。それぞれがもつ効果と視点を理解しましょう。
従業員満足度は職場に対する満足度の度合いを測る指標であるのに対し、従業員エンゲージメントは企業や組織を主体的に支えたいという強い意欲や愛着を示す指標です。満足度が高いからといって必ずしもエンゲージメントが高いとは限らず、逆にエンゲージメントが高くても現状に対する不満を感じているケースも起こり得ます。
たとえば、ある社員が給与や福利厚生には満足していないものの、企業の理念やビジョンに深く共感し、自ら積極的に提案を行っている場合はエンゲージメントが高いと考えられます。一方、待遇は比較的良いものの、大きな目標に共感できず惰性で仕事をしている社員は従業員満足度は一定以上あってもエンゲージメントは低い状態です。
このように、従業員満足度とエンゲージメントは企業活動の異なる要素に影響を与えます。両方のバランスをうまく取ることが、従業員一人ひとりのパフォーマンスを最大化し、組織としての真の成長につながるポイントです。
従業員満足度が組織にもたらすメリット
従業員満足度が高い企業には、具体的にどのような利点があるのでしょうか。
従業員満足度を高めることで得られる効果は、企業経営にとって非常に大きなインパクトをもたらします。業務に前向きに取り組む従業員が増えると、組織全体の生産性と創造性が高まるため、新サービス開発などにおいてもスピードとアイデアの質が向上します。また、強いブランドイメージの確立にもつながり、市場での差別化要因として機能することが多いです。
柔軟な働き方を積極的に取り入れている企業では、社員の離職率低下や新規採用の強化が実現されています。さらに、顧客接点の多い企業の場合は、従業員が自社の商品やサービスを通じて良好な顧客体験を提供しやすくなり、結果的に顧客満足度の向上にもつながります。
ここでは、従業員満足度が組織にもたらす代表的なメリットをいくつかの視点に分けて見ていきましょう。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001166380.pdf
(新しい時代の働き方に関する研究会 報告書 参考資料 参照)
離職防止と優秀な人材の確保
従業員が職場に満足しているほど、長く働き続けたいと思う意欲が高まります。結果として離職率の低下につながり、人材流出によるコスト増大を抑えられるメリットが生まれます。優秀な人材を引き留められるかどうかは企業の成長に直結しており、福利厚生や評価制度などの充実がこの部分を支える大きな要因となっています。
従業員モチベーションおよび生産性の向上
従業員が自分の仕事にやりがいを感じられれば、自然とモチベーションが高まり、積極的な行動や学習意欲が生まれます。その結果、業務効率や生産性が向上し、新しいアイデアや付加価値を生む機会が増えます。実際に、人事評価制度の透明性を高めた企業では、チャレンジを後押しする企業文化が育まれています。
顧客満足度(CS)への好影響
顧客の満足度を高めるためには、先に従業員のやる気や誇りを高めることが近道となります。従業員が明るく前向きな態度で接客やサービス提供を行うと、顧客も企業を高く評価しやすくなります。結果的にリピーターやクチコミが増え、企業の収益を安定させる力となるのです。
企業イメージやブランド力の向上
従業員が自社を誇りに思い、積極的に情報を発信することで、企業の社会的イメージは大きく向上します。昨今はSNSなどを活用して社員が社内の魅力を発信する機会も増えており、こうしたポジティブな情報発信は採用面でも有利です。企業イメージが上がると、売上や投資家からの評価にも良い影響が期待できます。
従業員満足度が低い場合に生じるリスク
逆に従業員満足度が低下すると、企業にはどのような悪影響が及ぶのでしょうか。
従業員満足度が低いまま放置されると、企業の業績や組織運営にマイナスの影響が広がります。やる気のない状態からはイノベーションが生まれにくく、対外的にも企業価値を下げてしまうリスクが高まります。ここでは、代表的なリスクとして人材流出と組織全体のパフォーマンス低下を取り上げます。
人材流出による採用コスト増大
従業員満足度の低下は、直接的に離職率を高める要因になります。優秀な人材が抜けると、企業は新たな採用と育成コストを負担しなければなりません。さらに、離職した従業員のノウハウや顧客との関係性が失われるという機会損失も見過ごせない問題です。
組織全体のパフォーマンス低下
モチベーションの低い従業員が増えると、組織全体の生産性が下がり、社内コミュニケーションにも悪影響を及ぼします。特にサービス・製造業など現場でのチームワークが求められる業種では、業務品質の低下が顧客満足度の低下を招く恐れがあります。こうした悪循環を防ぐためにも、従業員満足度の継続的なモニタリングと改善が必要です。
従業員満足度を構成する主な要素

従業員満足度を考えるうえで欠かせない、代表的な要素を具体的に見ていきます。
従業員満足度を左右する要因は多岐にわたりますが、給与や評価制度といった直接的な待遇面だけでなく、企業理念の共有やコミュニケーション環境など、ソフト面の重要性も見逃せません。実際に、グローバルで評価が高い組織では、給与だけでなく心理的安全性の高さや共通のビジョンに共感した働き方が実現されています。
一般的には、給与や福利厚生といったわかりやすい要素に目が向きがちですが、キャリア形成支援や学習機会の提供も従業員満足度をさらに高めるうえで不可欠な取り組みです。ここでは、それぞれの要素がどのように従業員の満足度に寄与するのかを見ていきます。
納得感のある給与・評価制度
給与やボーナス、評価制度は、従業員満足度を構成するうえで最も直接的に影響を及ぼす要素のひとつです。成果が正しく評価されていると感じられれば、社員は自分の役割をよりポジティブに捉えやすくなります。逆に不透明さや不公平感があると、モチベーションを大きく損ねる可能性があるため、制度設計と運用の透明性が重要です。
充実した福利厚生と健康経営
有給休暇の取得促進や健康診断、育児休暇制度など、社員が安心して働ける環境を整えることは企業の重要な使命です。特に海外では、企業内にジムやカフェテリアを設ける事例が一般的になりつつあり、日本でもオフィスカフェやリラクゼーションスペースを導入する企業が増加しています。こうした取り組みは直接的な生産性向上だけでなく、働く意欲や帰属意識の向上にも結びつきます。
企業理念・ビジョンへの共感
企業が掲げる理念やビジョンに従業員が共感できるかどうかは、エンゲージメントを高めるカギとなります。明確な方向性を示し、それを具体的な行動指針として落とし込むことで、社員は自分の業務が組織の大きな目標にどう結びつくかを実感できます。その結果、やりがいや責任感が育まれ、企業の成長を共に目指す気運が高まります。
働きやすい職場環境とワークライフバランス
物理的なオフィス環境や、テレワークなどの柔軟な働き方を可能にする制度は、従業員満足度に大きく影響します。通勤時間の削減やフレックスタイム制度の導入など、働く人のライフスタイルに合わせた取り組みを進めることで、家庭や自己啓発とのバランスを取りやすくなります。実際にワークライフバランスを重視する企業は、長期的な視点で見ても高い業績を維持しやすい傾向にあります。
オフィス環境を快適にするサービスを展開するダイオーズでは、さまざまなウォーターサーバーを取り揃えておりますので、ぜひご覧ください。
良好なコミュニケーションと人間関係
上下関係や部門間に壁があると、従業員の満足度は低下しやすくなります。風通しの良いコミュニケーションが確立されることで、アイデアの提案や問題の早期発見がスムーズに進み、チームワークの向上にもつながります。これには上司と部下の信頼関係や社内SNSなどのデジタルプラットフォームを活用した情報共有が効果的です。
キャリア形成や学びの機会
キャリアアップのための支援制度や研修、学習の機会が充実していると、従業員は将来の成長に希望を持ちやすくなります。例えば、研修制度の拡充で従業員のスキルを高めたり、異動自由化でキャリアを多角的に構築できる仕組みを取り入れている企業では従業員満足度も向上傾向にあります。こうした環境があると、仕事へのモチベーションや組織へのロイヤルティが強まります。
厚生労働省が従業員満足度向上を推進する背景
国としても従業員満足度を高めることを推奨する背景には、どのような狙いがあるのでしょうか。
厚生労働省は、過重労働による健康被害や少子高齢化による労働力不足が社会問題化している現状を踏まえ、従業員が安心して働き続けられる環境づくりを推進しています。その一環として、働き方改革関連法の実施や健康経営の奨励など、企業側の取り組みを後押しする施策が充実化してきました。従業員の満足度を高めれば、労働生産性の向上だけでなく、医療費の抑制や社会保障負担の軽減といった面でも社会的なメリットが大きいと期待されています。
出典:
https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/home/sintyaku_itiran/engagimento_20240207.html
(厚生労働省「今後の雇用政策の実施に向けた現状分析に関する調査研究事業」(平成27年) 参照)
従業員満足度を計測する方法
現状を正しく把握するための指標として、どのような調査方法が効果的かを解説します。
従業員満足度の向上施策を立案するには、まずは正確な現状把握が欠かせません。アンケート調査やインタビューなど、定量調査・定性調査を組み合わせることで、組織の課題や従業員の本音をより深く掴むことが可能になります。また、近年ではeNPSなどの新しい評価手法も注目されており、さまざまな角度から従業員の満足度を測ることが重要です。
出典:https://emotion-tech.co.jp/column/2019/what_is_enps_with_case/
(eNPS℠とは?従業員エンゲージメント向上のための指標を事例付きで解説! 参照)
アンケートやサーベイツールの活用
最も一般的な手法として、全社的にアンケートを実施する方法があります。オンラインサーベイツールなどを使うと回答の集計も自動化でき、大量のデータを効率的に分析可能です。設問の内容や頻度によって得られる情報の質が変わるため、やみくもに実施するのではなく、目的を明確にしたうえで設計することが大切です。
面談・インタビューによる定性調査
アンケートでは掴みきれない従業員の悩みやモチベーションの源泉を把握するには、直接対話が有効です。心理的安全性を保証したうえで個別にヒアリングすると、より深い本音や潜在的な課題を洗い出すことができます。管理職が日常業務の中で定期的にワンオンワン面談を行う企業も増えています。
eNPSで組織の推奨度を把握する
eNPS(Employee Net Promoter Score)とは、従業員がどの程度自社を友人や知人にすすめたいと思うかを数値化した指標です。簡潔な質問で集計しやすいため導入も容易で、組織全体の“健康度”を把握するのに役立ちます。eNPSの結果を定期的に追跡し、施策の効果検証に活用する事例が国内外で増えています。
従業員満足度向上の基本ステップ
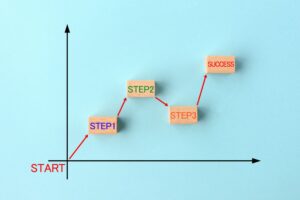
従業員満足度を改善していくために、どのようなステップを踏めばよいのでしょうか。
従業員満足度を向上させるには、一度きりの施策ではなく、継続的な改善サイクルを回す仕組みづくりが不可欠です。問題の本質を見極め、効果的なアクションを繰り返しながら組織文化に定着させることで、長期的に高い従業員満足度を維持することができます。ここでは、一般的なプロセスに沿ったアプローチを紹介します。
1. 現状把握と課題の明確化
まずはサーベイやヒアリングを通じて、従業員がどのような点に不満を抱えているかを洗い出します。数字だけではなくコメントやインタビュー記録を丁寧に確認し、本質的な問題を整理しましょう。ここで見つかった優先度の高い課題が、次の施策立案の基礎になります。
2. 施策の立案と優先度の設定
課題が明確になったら、それぞれに対して改善策をリストアップし、実行の難易度や期待される効果を検証します。すべてを一度に解決しようとするのではなく、優先度の高いものからアプローチするのが賢明です。具体的な数値目標やスケジュールも設定し、取り組みを組織全体で共有することが重要です。
3. 施策の実行と従業員の巻き込み
計画した施策を実践に移す段階では、現場の従業員が納得感を持って参加できるよう十分な情報共有が必須です。たとえば、試験導入の段階で積極的にフィードバックを集め、都度改善を図りながらスムーズに全社展開していくと失敗を最小限に抑えられます。施策に協力する従業員同士のチームビルディングを支援する取り組みも効果的です。
4. 効果測定と継続的な改善
施策を実行したら、その成果を定期的に評価し、数値的なデータと定性的な情報の両面から検証を行います。改善が必要な点が見つかればすぐに対策を講じ、次の施策に反映させることで、従業員満足度をより高めるサイクルを築くことができます。こうしたPDCAが機能している企業は、長期にわたって従業員から選ばれる職場を実現しやすいです。
取り組みをスムーズに進めるためのポイント
従業員満足度向上施策を効果的に推進するコツを紹介します。
組織として従業員満足度の改善に本腰を入れる場合、施策そのものの内容だけでなく、それを実行するプロセスや体制が大切です。とくに経営陣と管理職が一体となって取り組む姿勢を示すことで、より高いレベルでの成果が期待できます。また、速やかなフィードバック体制やPDCAの徹底など、日常的に改善を回す仕組みづくりも重要です。
経営陣と管理職のコミットメント
トップマネジメントが従業員満足度向上の意義を理解し、先頭に立って取り組むことで、組織全体へのメッセージが明確になります。管理職レベルも目標やビジョンを共有し、チームの方向性をしっかり示すことが欠かせません。こうした一貫性のある姿勢によって、従業員が「会社が本気で取り組んでいる」と感じられるようになるわけです。
従業員の意見を早期にフィードバックする仕組み
アンケートや面談などで集めた従業員の声を、いかに早く経営や担当部署にフィードバックし、具体的なアクションにつなげられるかがポイントです。結果や改善策をきちんと共有しないと、従業員は「意見を言っても意味がない」と感じてしまう可能性があります。迅速なレスポンスとオープンなコミュニケーションが、従業員の信頼感を深めます。
PDCAサイクルで施策を改善し続ける
いったん導入した施策で一定の効果が出ても、環境やニーズは常に変化します。従業員満足度を高い水準で維持するには、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Act)のサイクルを回し続ける必要があります。柔軟かつ定期的に改善を重ねることで、社員一人ひとりの声に応えられる職場を実現できるのです。
従業員満足度と休憩スペース
オフィス環境の中でも休憩スペースは従業員のリフレッシュに大きく関わり、その満足度向上につながります。
近年、多くの企業でオフィスのリニューアルやレイアウト変更が進められていますが、その際に休憩スペースの充実を図る動きが活発です。疲れを解消し、同僚とのコミュニケーションを促す休憩スペースは、生産性向上のための大切な投資と考えられています。特にリラックスできるソファや軽食、自動販売機などを備えた空間は、従業員の満足度を高める効果が期待されます。オフィスに休憩スペースを設置するメリット・デメリットについてはこちらの記事もご覧ください。
オフィスカフェ導入事例
近年注目されているオフィスカフェの導入は、福利厚生やコミュニケーション促進に有効です。
海外企業だけでなく、日本国内でもオフィスカフェを導入する企業は増加傾向にあります。コーヒーや軽食を自由に楽しめるスペースを設けることで、従業員同士の情報交換やアイデア共有のタイミングが自然に生まれるようになります。休憩中のちょっとした会話からイノベーションが起きる可能性もあり、従業員満足度と企業力を同時に高める取り組みとして注目されています。
オフィスカフェ導入事例から空間づくりのポイントを知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
従業員満足度向上がもたらす今後の展望

企業の持続的な成長と社会的な要請の観点から、従業員満足度の向上はこれからますます重要になります。
従業員満足度に注力する企業ほど、長期的には優秀な人材が集まりやすく、業界内での競争力も高まります。社会の価値観が多様化する中で、従業員の働き方やキャリア観も多様になりつつあり、これらのニーズを先取りする企業が未来をリードすると考えられます。
日本企業における働き方改革との関連
日本政府が進める働き方改革は、ただ労働時間を短縮するだけでなく、働きがいや生産性を高めることに主眼を置いています。これにより、人事制度やオフィス環境を見直す企業が増え、その流れの中で従業員満足度の向上も重要課題として位置づけられているのです。改革が進むほど、より多様な働き方やキャリア形成が可能になり、ES向上との相乗効果が期待できます。
持続的成長のカギとしてのES向上
株主の利益を最優先とする経営スタイルでは、従業員満足度の向上は後回しにされがちでした。しかし、近年は企業価値を高めるうえで“従業員を大切にすることで生まれる持続的な成長”が注目を集めています。従業員が長く安心して働ける環境を整えることは、企業の社会的評価やブランドパワーを高める重要な要素として注目されているのです。
まとめ
従業員満足度向上は企業の成長と従業員の幸福度双方に寄与する取り組みです。ここまでのポイントを再確認し、実践的な施策につなげましょう。
本記事では、従業員満足度(ES)の基礎から実際の取り組み事例までを包括的に解説しました。従業員満足度が高い企業ほど離職率が低下し、顧客満足度やブランドイメージの向上につながるなど、多面的なメリットを享受できます。一方で、放っておけば人材流出や生産性低下といった深刻なリスクに直面することもあるため、早めの対策が必要です。
給与や福利厚生といったハード面だけでなく、組織のコミュニケーションや企業理念の共有などソフト面も重視することで、従業員が満足感とやりがいを感じられる環境を整えられます。また、厚生労働省が推進する働き方改革や健康経営との親和性も高く、社会全体の流れとしても今後さらに拡充していくと考えられます。
最終的に、従業員満足度向上の鍵は継続的な改善にあり、一度きりの施策では終わらせない粘り強さが大切です。現状把握→施策立案→実行→検証の流れをしっかり回し、積極的に社員の声を吸い上げて組織文化を育んでいくことが、企業にとって最大の成果をもたらすでしょう。