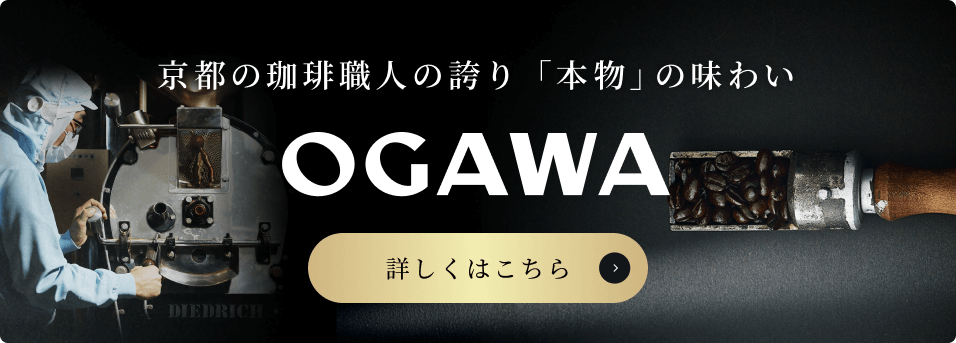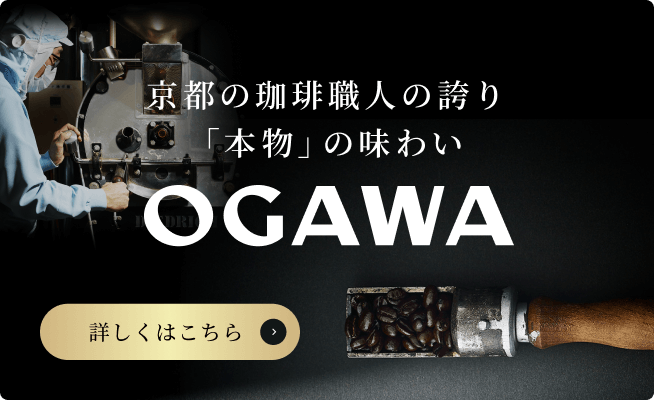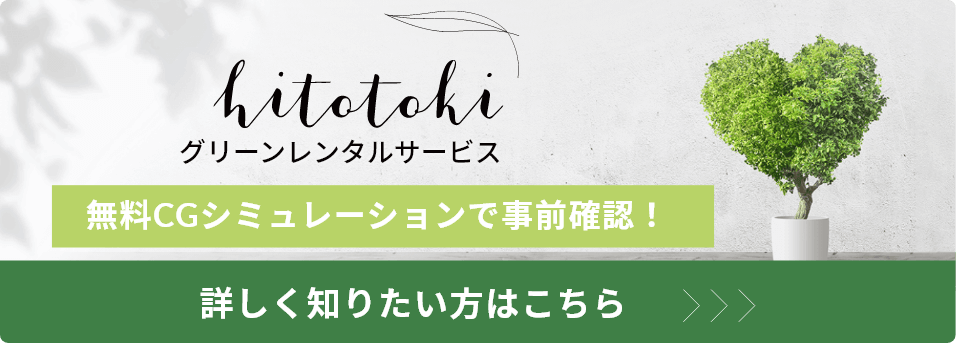近年、企業の社会的責任や人材確保の観点から、従業員の健康維持・増進を重視する“健康経営”が注目されています。新たな働き方や生涯労働が意識される中で、従業員が健康で意欲的に働ける環境を整えることは、企業にとって重要な競争優位の一つとなりつつあります。
健康経営の導入は、少子高齢化など社会構造の変化や医療費の増加など、企業を取り巻く経営課題への対応にも大きく貢献します。従業員の健康状態を把握・維持することで、生産性の向上や病気の早期発見、離職率の低減が期待できるからです。
本記事では、健康経営の定義やメリット、代表的な施策から実践手順、そして大企業・中小企業の事例に至るまでを幅広くカバーします。多様な企業規模に合わせた取り組みポイントを紹介し、専門家や保険者との連携方法にも触れることで、持続可能で効果的な健康経営の全容を詳しく解説します。
健康経営とは?その背景と必要性
企業が経営資源として従業員の健康を捉え、戦略的に施策を推進するという概念が健康経営です。ここでは、その定義と国内外での広がり、そして背景にある企業の役割について解説します。
企業が従業員の健康をしっかりとサポートすることで、長期的には企業価値の向上や安定した経営基盤に結び付くと考えられています。多様化する雇用形態や働き方改革の潮流の中でも、健康経営は従業員一人ひとりの健康状態を総合的に最適化し、活力ある職場を実現するための枠組みとなっています。
特に国内では、健康経営優良法人認定制度の導入により、従業員の健康管理に積極的に取り組む企業に注目が集まっています。評価されることで社会的信用が高まり、さらなる人材確保や企業イメージアップにつながる点も大きな特徴です。
また海外でも、健康関連施策への投資が企業価値を高める事例は多数報告されています。大企業はもちろん、中小企業においても健康投資に見合うリターンが得られるとの研究結果もあり、その必要性がますます高まっていると言えるでしょう。
健康経営の定義と国内外での推進の流れ
健康経営とは、従業員が心身ともに健康に働ける環境を整備し、経営的視点でその施策を推進する考え方です。経済産業省などが主体となって進める健康経営銘柄や健康経営優良法人認定制度など、国内の取り組みは年々活発化しています。
海外に目を向けても、アメリカでは“ウェルネス”プログラムやイギリスの“ヘルシー・ワークプレイス”など、企業規模や業態を問わず従業員の健康に配慮した施策が数多く導入されています。これらの背景には、新しい労働環境や社会課題への解決策として健康を重視する世界的な流れがあります。
日本企業も海外の事例を参考に、デジタルヘルスケアツールの導入や健康関連のイベント開催など、さまざまな方法で健康経営を推進しています。経営陣から従業員まで全員が健康に対して主体的に取り組むことで、企業全体の生産性や活気が高まる利点が多く見受けられます。
出典:https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_keiei.html
(健康経営(METI/経済産業省) 参照)
健康経営が注目される背景と企業の社会的責任
少子高齢化の進展や医療費の増加は社会保障制度に大きな影響を与えており、労働力不足や病気リスクの増加という課題が企業活動に直結しつつあります。従業員自身の健康リテラシーが上昇する一方で、企業が健康を考慮した経営を行わないと人材確保と競争力の維持が難しくなる状況です。
こうした背景から、企業には従業員の健康を守り、働きがいを育む社会的責任が求められています。健康経営は人材を活かすための最良の手段の一つであり、社会からの信頼を得るための重要な要素とも言えます。
さらに、環境や社会貢献を評価するESG投資の視点からも、健康経営は注目されるトピックとなっています。投資家や取引先からの評価を高めるうえでも、従業員の健康を経営に組み込み、持続的な企業成長を目指す健康経営は不可欠な取り組みとなっています。
健康経営のメリット

健康経営を導入するメリットは、単なる福利厚生にとどまらず、企業経営全体に好影響を与えます。ここでは代表的なメリットを解説します。
従業員が仕事に集中しやすい環境を整え、健康関連の問題を未然に防ぐことで企業全体の生産性が高まります。特に、個人の集中力向上がチーム全体の成果に波及し、プロジェクトの円滑な進行や顧客満足度の向上につながるケースが多くみられます。
また、健康経営を実践する企業に対しては、社会的な評価が高まりやすい点も魅力です。経営理念として健康を重視している姿勢は、就職活動中の若年層だけでなく幅広い年代の求職者からの支持を得る要因となります。
費用対効果の観点でも、従業員の離職や休職を減らすことで長期的にコストの削減が期待できます。健康経営は企業の成長のエンジンとなるだけでなく、企業ブランディングにも寄与する多面的なメリットを持っています。
生産性とモチベーションの向上
健康診断の結果をもとにした個別サポートや、定期的なストレスチェックの実施は、従業員が自身の健康と向き合うきっかけを作ります。こうした取り組みは一時的な意識向上だけでなく、業務の質を継続して向上させる要因となります。
モチベーションが高まると、自然と組織内のコミュニケーションも円滑になります。上司や同僚との距離が縮まり、相互理解が深まることで、従業員全体が積極的に業務に取り組む好循環を生み出します。
従業員が心身ともに健康であることは、企業の競争力を左右する重要な資産です。特に専門人材や熟練技術者ほど、健康的な環境での業務継続が企業価値を支える基盤となります。
企業イメージの向上と採用活動への好影響
健康経営に取り組む企業は、社外から“従業員を大切にする企業”としてポジティブに映ります。近年の求職者は、給与や福利厚生だけでなく健康面のサポートに注目して就職先を選ぶ傾向があります。
また、健康経営を通じて蓄積されたデータや取り組み実績は、PR活動や企業広告にも活用できます。実際に認証制度での評価が高い企業は、メディアやSNS上で好意的に取り上げられる機会が増え、ブランド価値の向上につながっています。
採用活動においても健康経営への取り組み方針を明確化することで、優秀な人材が企業を選びやすくなる利点があります。職場の雰囲気や働き方に配慮する企業文化が求職者の目に留まり、長期的かつ安定した人材確保を実現します。
従業員の離職率低下と人材定着
健康的な環境があることで従業員の身体的負担やストレスは軽減され、結果的に離職率が低下する傾向があります。日々の業務に安心感を持てる環境は、従業員が長く働き続けたいと感じる大きな要因になります。
人材の定着は企業にとって大きなコスト削減にもつながります。新たな採用・教育・研修にかかる時間や費用を最小限に抑え、既存従業員がスキルを蓄積していくことで、組織全体の知見が高まりやすくなります。
さらに、離職率が低い企業は“働きやすい職場”として社会的信用を得やすくなるため、企業ブランディングにもプラスの影響があります。人が定着しやすい職場作りは、健康経営を象徴する重要な指標の一つです。
健康経営を支える主な施策

健康経営を実践するにあたり、具体的な施策は多岐にわたります。代表的な取り組みを整理して、組織に合わせた活用例を考えてみましょう。
企業が行う健康施策には、身体面だけではなくメンタル面へのサポートもしっかりと含まれる必要があります。健康診断やストレスチェックを定期的に実施し、結果を踏まえて専門家がフォローアップを行うことで、未病や重症化予防に取り組むのが理想です。
また、子育てや介護など家庭の事情を抱える従業員への配慮も重要です。女性特有の健康課題へのサポートや、受動喫煙を防ぐ禁煙推進政策など、多様な視点で健康を守る施策が求められます。
そのうえで、産業医や保健師、外部の健康保険組合などとの連携を強化し、専門的なチェック体制や予防施策を充実させることが、健康経営の質を大きく左右します。
健康診断・ストレスチェックの実施とフォロー体制
定期的な健康診断は企業が提供できる最も基本的かつ重要な健康管理策の一つです。血液検査や身体測定の結果から個人の健康リスクを特定し、早期に対処することで重大な疾病の発症を防げます。
同時に、ストレスチェックの導入も欠かせません。従業員のメンタル面を把握し、必要に応じてカウンセリングや産業医との面談を行うことで、職場全体のメンタルヘルスを向上させることが可能になります。
これらの結果を従業員が安心して話せるように、プライバシーを確保した相談体制やフォローアップを確立することが大切です。適切なコミュニケーションの場を設けることで、未然にトラブルや離職を防ぐことにつながります。
産業医・保健師など専門家との連携
健康経営を推進するうえで、産業医や保健師の専門知識は非常に有用です。経営者が健康について正確かつ包括的なサポートを行うためには、医療や保健のプロフェッショナルとの協力が欠かせません。
産業医は従業員一人ひとりの健康データを活用し、個別のリスク評価やフォローアップを行うことができます。職場での作業環境を確認して改善点を提案するだけでなく、メンタルヘルスも含めて総合的に従業員を支援します。
また、保健師が中心となって健康教育や生活習慣改善のサポートを実施する形も効果的です。こうした社内外の専門家チームを活用することで、健康経営の取り組みはより具体化し、継続的に成果を上げられます。
女性の健康課題への対応と環境整備
女性の健康課題には、妊娠・出産や更年期など男性にはないリスク要因が含まれます。これらの事情を理解し、柔軟な労働時間制度や休暇制度を整えることで、女性が安心して働ける環境を作ることが重要です。
特に出産前後のサポートや育児休暇復帰後の時短勤務などは、女性に限らず家族を持つ従業員全員にとって働きやすい体制となります。結果的に企業の多様性確保や人材力の強化にもつながるでしょう。
女性特有の体調不良に対する相談窓口を設けたり、職場での生活指導やセミナーを開催したりする企業も増えています。小さな配慮の積み重ねが従業員の定着や意欲向上につながり、企業全体の活力を生み出します。
禁煙対策・受動喫煙防止を通じた健康リスク軽減
喫煙は心疾患やがんなどさまざまな疾病リスクを高める要因とされています。従業員の健康を守るためには、社内の分煙措置や喫煙スペースの制限などルール作りが必要です。
また、受動喫煙による健康被害は喫煙者だけではなく非喫煙者にも及びます。オフィス内での禁煙化を進めることで、従業員全員にとって清潔で快適な作業環境を提供することが可能になります。
禁煙プログラムへの参加や個別カウンセリングなどのサポートを提供し、段階的に喫煙者の習慣改善を促す企業も増えています。こうした取り組みは長期的な医療費の削減や疾病予防にも大きく寄与します。
取り組みをはじめるための手順
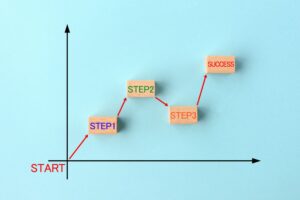
健康経営を円滑に進めるには、具体的なステップを踏むことが大切です。ここでは計画立案から定期的な振り返りまでのプロセスを解説します。
計画を立ち上げる段階では、経営層が主導して健康方針を示し、組織内での優先度を明確にすることが大切です。従業員への周知や意識づけをしっかり行うことで、初期段階から施策への理解が深まり、スムーズな導入が期待できます。
次に、専任担当者や推進チームを設けることで、実際の施策管理とスケジュール調整が円滑に進みます。部署横断的に連携しやすい体制を作ることで、総合的な健康管理に取り組みやすくなるでしょう。
施策を始めたら、定量的・定性的な指標を用いて評価と改善を繰り返すことが重要です。実施後の従業員満足度調査や健康データ分析から得られた結果を踏まえて、より最適な施策へとアップデートしていきます。
STEP1:健康宣言の実施と経営層のリーダーシップ
まずは経営トップが健康経営の意義を理解し、具体的な健康宣言を表明することが出発点となります。企業全体で取り組む姿勢が明確化されることで、従業員のモチベーションや社内外からの信頼を得やすくなります。
トップダウンでの宣言があると、組織全体に健康経営が必須テーマとして認知され、中長期的な投資や人的リソースの確保にもつながります。特に中小企業では、社長自らが健康経営のメリットや重要性をアピールすることで理解がスムーズに進むことが多いです。
経営層のリーダーシップが戦略の方向性を決めるだけでなく、従業員に対するメッセージとしても大きな意味を持ちます。この初動の段階での姿勢が、後々の施策の進み具合や定着度を左右します。
STEP2:専任担当者の配置と推進組織の構築
健康経営をスポット的な施策で終わらせないためには、継続的な運用とマネジメントが不可欠です。そのためには、社内に専任の担当者や部署を設置し、定期的に会議やイベントを企画・実施できる体制を整える必要があります。
推進組織では異なる部門の担当者が参画し、人事部、総務部、経営企画などと連携を取る形が好ましいです。幅広い視点から施策を検討し、従業員の多様なニーズを汲み取ることができます。
外部の専門家や健康保険組合とも連携する形で情報収集を行い、最新の健康施策や業界事例を共有することも効果的です。組織横断的な体制が整うことで、健康経営の方針はビジネスのあらゆる場面に浸透しやすくなります。
STEP3:従業員参加型の施策検討と社内周知
健康施策を実施する際には、従業員の声を反映させることが欠かせません。アンケートやヒアリングを通じて、実際に求められているサポートを的確に把握することで、参加意欲の高い施策が生まれます。
具体的には、ウォーキングキャンペーンや社内イベントなど、従業員同士が楽しみながら健康を意識できる場を提供すると効果的です。職場のコミュニケーション活性化にも寄与し、チームワークを高めるきっかけになります。
社内周知の段階では、メールやポスター、SNSなど多様な手段を活用し、参加を促すのがおすすめです。従業員一人ひとりが自分事として捉えられるように情報を共有し、積極的な参加を呼びかけることが重要となります。
STEP4:継続的な評価と課題抽出、改善サイクル
健康経営に絶対的なゴールはありませんが、定期的な評価と改善によって常にその質を高め続けることが可能です。健康診断結果やアンケートでの従業員満足度など、定量・定性の両面から評価指標を設定しましょう。
施策実施後には、得られたデータを元に改善策を検討し、次の施策計画へ反映させます。例えば健康リスクが多い分野を優先的に強化するなど、費用対効果の高いアプローチを選択しやすくなります。
このサイクルを回す中で、企業文化に根差した健康経営の仕組みが進化し、従業員と企業の双方にメリットをもたらす結果につながるでしょう。
出典:
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkokeiei-guidebook2804.pdf(企業の「健康経営」ガイドブック~連携・協働による健康づくりのススメ~(改訂第1版) 参照)
健康経営の取り組み事例

実際に健康経営で成果を上げている中小企業の事例を紹介します。大規模な施策だけでなく、日々の業務に取り入れやすい取り組みも合わせて解説します。
各社の成功事例を参考にすることで、自社の事業内容や規模に適したアイデアを得られます。中小企業の場合は、細やかなコミュニケーションを武器にしたきめ細かいサポート施策を実施するなど、各社の状況に合わせた工夫が結実しています。
ここでは、運動習慣の定着やメンタルヘルスサポート、保険者との協力など多彩な事例を取り上げます。自社で活用できる要素は積極的に取り入れ、必要に応じてカスタマイズすることで、より効果的な健康経営を実現できるでしょう。
事例1:電子万歩計を活用したウォーキングコンテスト
中小企業の例として、電子万歩計を活用して従業員の歩数を集計し、チーム対抗で競うウォーキングコンテストを実施したケースがあります。この取り組みにより、従業員は楽しみながら運動習慣を身につけることができ、健康意識の向上につながりました。
この施策は、従業員同士が日々の歩数を共有し合うことで、社内コミュニケーションの活性化にも貢献しています。
事例2:保険者との協力で実現する健康サポート
中小企業では、大規模な設備投資が難しいケースも多いため、外部の協力を得ることが重要です。例えば、健康保険組合と連携し、従業員への情報提供や健康相談窓口を充実させた事例があります。
ある企業では、専門家を招いた食生活セミナーやメンタルヘルスに関する講習会を定期的に開催。費用は保険組合の補助を活用することで、自社のコスト負担を抑えながらも、専門性の高い健康サポートを実施しています。
事例3:セルフチェックシステムを導入し、健康リテラシー向上を推進
ある企業では、従業員の健康意識を高めるために、セルフチェックシステムを導入しました。このシステムでは、血圧や体重などの測定データを基に、将来の健康状態の予測や個別アドバイスが自動的に出力されます。これにより、従業員は自身の健康状態を把握し、生活習慣病予防への意識を高めることができています。
出典:
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/kenkokeieiyuryohojin_jireisyu200327.pdf(健康経営優良法人取り組み事例集 参照)
成功する健康経営のポイント

健康経営を実践・継続するうえで押さえておきたい重要なポイントを整理します。目標設定や従業員の主体的参加など、取り組みの質を高めるためのヒントです。
健康経営を成功に導くためには、明確なゴールと指標を設定し、具体的な行動につなげることが大切です。特に、部署別の健康指標を用いるなど、細かな単位で状況を把握して改善を加えると効果が上がります。
また、従業員の意見を積極的に取り入れ、ボトムアップで施策を充実させることも重要です。リーダーシップと現場の声を組み合わせることで、従業員全体のモチベーション向上を促します。
外部の専門家を招いて知見を得たり、展示会やセミナーで新しい技術やサービスを探したりすることは、健康経営の幅を拡げるのに有効です。常に最新情報を収集することで、自社の取り組みを適切にブラッシュアップできます。
目標設定とKPI管理による施策の可視化
健康経営を具体化するうえで欠かせないのが、KPI(重要業績評価指標)の活用です。健康診断受診率やストレスチェック回答率、生産性向上の度合いなどを数値化し、企業全体で進捗状況を共有します。
これにより、施策に対する意識が組織全体で高まりやすくなり、適切なタイミングでリソースを投入しやすくなります。データを根拠としてPDCAサイクルを回すことができ、施策の改善点も明確化されます。
さらに、KPIを公表することで、従業員が自分の行動が企業全体の数字に貢献していると感じやすくなり、健康施策への主体的な参加を促す効果も期待できます。
従業員が主体的に参加できる仕組みづくり
健康経営を定着させるには、従業員一人ひとりが“健康づくりの主役”になる感覚を持つことが大切です。イベント型の施策だけでなく、日常的に健康を意識できる制度やツールを整備しましょう。
例えば、昼休みの短いアクティビティやフレックスタイム制度の活用で、仕事の合間に無理なくリフレッシュできる環境を作るなど、取り組みやすい施策を用意しておくと効果的です。
また、社内SNSやアプリを通じて健康情報や実践報告を共有する仕組みを導入すれば、従業員同士が刺激し合い、健康意識が自然と高まります。
専門家や関連イベントを活用した情報収集
健康経営に関する情報は日々アップデートされており、専門家の見解や業界トレンドを取り入れることで施策の精度が増します。産業医や保健師はもちろん、医療機関や大学などの外部組織との連携を検討することも一つの方法です。
さらに、市町村や保険組合が主催する健康関連イベントやセミナーに参加すると、最新のヘルスケア技術や事例を効率的に収集できます。参加者同士のネットワーク形成も大きなメリットとなるでしょう。
複数の情報源から得た知見を組み合わせ、自社の文化や従業員の特性に合わせてカスタマイズするのが理想です。先進事例を漫然と真似るのではなく、自社に最適化した形で取り入れることが持続可能な健康経営の鍵となります。
設置型の社食で支える健康経営

従業員の食生活改善は、健康経営の一環として非常に効果的です。ここでは設置型社食サービスの活用例を紹介します。
忙しい日々の中で、手軽に栄養バランスの整った食事を取ることは簡単ではありません。設置型の社食サービスを導入することで、従業員が安定的に良質な食事を摂取できる環境を整備することが可能です。
食育の観点からも、社食での摂取カロリーや栄養素を分かりやすく表示すれば、健康意識が高まります。個人の趣向やアレルギー対応にも柔軟に応えられる点が、現代の多様な働き方にフィットするメリットとなります。
こうした取り組みは、会社全体の健康水準を向上させるだけでなく、社内コミュニケーションの活性化にも役立ちます。昼食や休憩時間に自然と情報交換が行われ、従業員同士の絆が深まる効果も期待できます。従業員の健康を支える食事の重要性についてはこちらの記事もご覧ください。
ダイオーズの設置型の社食サービス
ダイオーズでは、福利厚生の一環として設置型の社食サービスを提供し、健康志向のメニューを安定的に供給しています。社食導入により、忙しい従業員でもカロリーや栄養バランスを考慮した食事をとりやすくできるようなサービスです。
従業員が購入する際は、現金の持ち合わせがなくてもスムーズに購入できるよう、スマートフォン、クレジットカード、電子マネーなど、幅広い決済方法に対応してとても便利にご利用いただけます。※電子マネー決済をご希望の会社様は別途、手続きが必要となります。
まとめ
健康経営は、企業と従業員の双方に多大なメリットをもたらします。自社に合った施策を段階的に導入し、継続的に評価・改善していくことで、より強固な経営基盤と働きやすい職場環境を実現できるでしょう。
健康経営の取り組みは、単なるコストではなく、企業の未来への投資として考えられます。従業員が健康で高いモチベーションを保つことで、生産性向上や人材の確保・定着など、多くの成果を生み出します。
大企業では大規模なプログラム、中小企業では重点的かつ柔軟な取り組みといった形で、それぞれの規模や文化に合わせた導入が重要です。経営層から専門家、従業員までが一体となり、PDCAサイクルを回しながら施策を成長させていくことで、真の健康経営が実現します。
まずは身近なところから情報収集や小規模な施策を始め、成功事例やデータをもとに少しずつ拡大していくのが得策です。健康経営の定着は一朝一夕では実現しませんが、地道な努力こそが企業を持続的にサポートする大きな力となるでしょう。