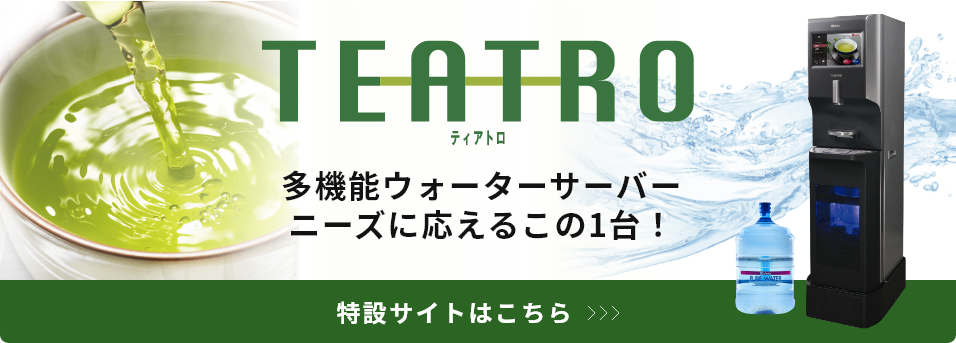水道水のpH値は、水を安心して飲用するうえで確認しておきたい重要な指標です。pHは酸性やアルカリ性の度合いを示し、数値によって性質が大きく変わります。普段意識していなくても、料理や洗浄など、あらゆる場面に影響を与える要素といえるでしょう。
日本の水道水は、高度な管理体制のもとで飲用基準が定められており、世界的にも水質が良いことで知られています。pHはこの安全性を支える要素の一つであり、適切な数値範囲を保つことによって健康を害するリスクを最小限に抑えているのです。
本記事では、水道水のpHについての基本知識から、法律上の基準、酸性・アルカリ性の特徴、さらには料理の味や利用シーンへの影響まで幅広く解説します。pHを正しく理解することで、水を使う毎日の生活が一層快適かつ安全になるでしょう。
pHの基本:酸性・中性・アルカリ性の違い
pHは水の性質を理解するうえで最初に押さえておきたい指数です。
pHは0から14までの数値で表され、7が中性、7より小さいほど酸性、7より大きいほどアルカリ性を示します。水が酸性に寄ると、金属を溶かしやすくなるなどの特性を持ち、一方でアルカリ性はタンパク質を溶かす力が強いとされています。この数値は水の味わいや用途にも大きく関わってくるため、私たちが普段何気なく利用している水道水についても理解を深める価値があります。さらにpHは、生物が生きる環境や、電子機器の腐食にまで影響を及ぼすので、幅広い分野で測定と管理が行われているのです。
pHが示す数値と人体への影響
水道水などの飲用水であれば、過度に酸性やアルカリ性に偏っていなければ大きな問題は起きにくいとされています。ただし、pHが極端に低い酸性水や高いアルカリ性水は胃腸への刺激が強く、体調に影響を及ぼす可能性があります。また、肌に触れる場合にも、適正pHから大きく外れた水は肌荒れや乾燥の原因になることがあるため、身体に使う水のpHにはある程度の注意が必要です。なお、日本の水道水は基準値が厳しく設定されているので、通常の利用で健康に支障をきたす可能性は低いといえるでしょう。
出典:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=79aa4934&dataType=0&pageNo=1(水質基準に関する省令 参照)
中性pH7が飲み水の基準値となる理由
pH7は酸性やアルカリ性の影響が最も少ない“中性”を示し、多くの生物が生存する環境に適した領域とされています。飲み水としては、酸味や苦味などのクセが少なく、様々な調理や洗浄に使いやすいという特徴があります。さらに、中性に近い水は水道管や機器の腐食リスクも小さく、安全性や維持管理の面からも最適とされます。このような理由から、pH7近辺が飲用に適したバランスだと広く認められているのです。
水道水のpH基準値と法律上の取り決め

日本の水道水は法律によってpH値の範囲が細かく定められており、厳格な安全基準をクリアしています。
水道水に関する基準は厚生労働省が管轄し、水道法によってpH値は5.8〜8.6の範囲に収まるように定められています。この基準が設定された背景には、人体への悪影響や水道設備の腐食防止など多角的な観点があります。また水道水は塩素消毒などの処理を経ており、処理工程でpHが適切な範囲になるよう調整されます。こうした法制度と自治体の水質検査によって日本の水道水は世界的に見ても非常に高い安全性を保っているのです。
5.8〜8.6に定められている根拠
この範囲は、騒音や細菌といった別のリスク要因も含め、総合的に人体や環境に有害性が低いと判断された数値帯です。水のpHが低すぎると配管が腐食しやすくなり、そこから噴出する金属成分が健康を損ねる要因になる可能性があります。反対にpHが高すぎると独特の苦味やヌメリ感を伴うことがあり、飲用に適した味わいを保てません。そうした幅広い観点を踏まえて、5.8〜8.6の間に設定されているのです。
日本の水道水が安全と言われる理由
国や地方自治体が定期的に行う水質検査や最新設備の導入によって、安定したpH管理が可能となっています。そこには、浄水場での細かなろ過工程や消毒処理の徹底が含まれ、水が配管を通じて家庭に届くまで何度もチェックが行われます。また日本特有の豊富な水資源にも助けられており、比較的硬度が低い軟水が主流のため、微生物や化学物質の影響が少ないことも挙げられるでしょう。結果として、世界でも有数の安全な飲用水を家庭の蛇口から得られるのです。
出典:https://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/09/dl/s0904-4f2.pdf(水道法第4条に基づく水質基準 参照)
アルカリ性水・酸性水の特徴と使い分け
飲用に適した中性付近のpHだけでなく、アルカリ寄りや酸性寄りの水を上手に活用することも重要です。
家電などを使えば家庭内でアルカリ性や酸性に調整した水を比較的容易に作れます。アルカリ性は料理の抽出力向上や飲み口のまろやかさを得るために活かされ、一方で酸性の水は洗浄や殺菌効果を高めたい場面で役立つとされています。性質を知ることで、キッチンや洗面所での利用シーンを広げられるだけでなく、素材や調理方法との相性によって食材本来の旨味を引き出せる点も魅力です。
アルカリ性の水:料理や飲み水への活用例
アルカリ性の水は、コーヒーや紅茶などの抽出飲料の風味を引き立てると同時に、ホットケーキの膨らみを良くするなど調理法でも活躍します。さらに、アルカリ性の水に漬けることで野菜のアクを和らげ、下ごしらえを効率的に行えることも利点です。家庭でウォーターサーバーやアルカリイオン整水器を利用している場合は、適度にアルカリ性を保った水を料理に使う工夫をすることで味わいが段階的に変わることを体感できます。
酸性の水:手洗いや洗浄に適した理由
酸性の水は、雑菌や皮脂汚れに対して高い洗浄効果を発揮するとされ、手洗いをはじめとする衛生管理の面で利用できます。資源や環境への配慮を考えると、強い洗剤だけに頼らず、適度な酸性水を活用することで汚れをしっかり落としながら肌への負担を軽減できるメリットがあります。ただし、酸性の度合いが強いと肌に刺激を与える可能性もあるため、実際に使用する際には自宅の機器で生成した水のpHを確認しながら使うことが推奨されます。
水道水・ミネラルウォーター・RO水のpH比較

飲料水として利用される選択肢は水道水だけではありません。各種ミネラルウォーターやRO水にも注目が集まっています。
スーパーやコンビニで手軽に入手できるミネラルウォーターは、地層を通って自然に濾過された水であり、地域や採水地によってpHや含まれるミネラルの種類が異なります。一方、RO水は逆浸透膜を使い、不純物を極力取り除いた“限りなく純水に近い”水です。これらの水をpHの観点で比較すると、水道水と大きく変わらないものからミネラルの影響でややアルカリ性寄りになるものまで様々あります。飲む目的や好みに応じて選ぶことで、理想的な水の性質を得やすいでしょう。
理想的な純水(pH7)とRO水の特徴
理想的な純水はpH7を示す中性の水ですが、実際には空気中の二酸化炭素と触れることで弱い酸性を帯びることがあります。RO水は逆浸透膜という細かいフィルターを通すことで、水以外の溶解成分をほぼ除去した状態に近くなるため、味や匂いがほとんどなくスッキリとした飲み口が特徴です。雑味を極力排除したい場面や、限られた成分しか入れたくない調理に最適ですが、ミネラル補給という面では一般のミネラルウォーターや水道水の方が優れるケースもあります。
ミネラルウォーターのpHは水道水とどう違う?
ミネラルウォーターは、採水地の地質や地層を通る過程でミネラル分が自然に溶け込み、メーカーやブランドごとにpHの傾向が異なります。一方で、日本の水道水は主に中性を保つように管理されているため、販売されているミネラルウォーターと大きくかけ離れたpH値になることはあまりありません。硬度や含有成分量が変化すると味にも違いが出るため、飲み比べると微妙な口当たりの差を楽しむことができます。
硬水・軟水とpHの関係
硬度とは主にカルシウムやマグネシウムなどのミネラル成分の量を示し、日本の水道水は軟水に分類されるケースがほとんどです。一般的に硬度が高い水は少しアルカリ性寄りになることがありますが、pH自体を決定づける要因は他にも多いので必ずしも硬水=アルカリ性とは限りません。ただし、硬度の高い水は苦味を感じやすい場合もあるので、飲みやすさや料理の仕上がりに影響する可能性があります。日常の利用では、好みや用途に合わせて硬度とpHを考慮に入れるとよいでしょう。
pHが料理と味に与える影響

水が変われば味が変わると言われるほど、pHは料理にも大きく関係します。
例えば、お湯で煮る、出汁を抽出する、米を炊くなど、水と食材が密接に触れ合う工程では、水のpHが味や色合いを左右します。アルカリ性の水は食材の繊維をやわらかくしたり、出汁の抽出効率を高めたりすると言われ、一方で酸性寄りの場合はさっぱりした後味や食材の発色維持に寄与することがあります。きちんとpHに注目できれば、素材本来の特徴をより活かした料理作りが可能になるでしょう。
アルカリ性の水が向いている調理例
煮物や煮込み料理、出汁をとる際などは、アルカリ性の水が非常に役立ちます。煮物の場合、食材に含まれるタンパク質が溶け出しやすくなり、旨味やコクのある煮汁が得られるメリットがあります。また、米を炊くときにアルカリ性の水を用いれば、よりふっくらと炊き上がることが多いとされ、食感や甘みも引き立つという意見もあります。ただし、人によっては柔らかすぎると感じる場合もあるため、適度な加減を見極めることが必要です。
酸性寄りの水が生かせる料理・用途
酸性寄りの水はフルーツや野菜の変色防止に役立ち、りんごやじゃがいもを切った後に酸性水へ漬けることで色の変化を抑えることができます。加えて、酸味が特徴のスープやソースを調理する際には食材の風味を強調しやすく、味にキレを与えてくれる場合があります。料理によっては酸味が強調され過ぎないように調整が必要ですが、うまく使うことで料理の奥行きが広がるのは大きな利点といえるでしょう。
pHの測定方法と注意点

家庭でも手軽に水のpHを計測できるツールがあり、使用している水の性質を簡単にチェックできます。
pHは水の性質だけでなく、土壌や食品など多種多様な場面で測定されるため、方法も複数存在します。家庭では、試験紙や簡易キットを使っておおまかな数値を把握し、必要に応じて専用の計測器を導入してより正確な数値を確認することが多いです。測定結果は温度や空気に触れる時間によって変化する可能性があるため、なるべく迅速かつ同じ条件で測ることがコツとなります。
試薬・pH試験紙による簡易測定
試験紙を使う方法は安価でありながら手軽に結果を得られることが利点です。水をコップなどに取り、pH試験紙を浸して色の変化を比色表と照合することでおおよその値を知ることができます。数値の精度は専門機器に及ばないものの、定期的にチェックするだけでも飲用水の異常や急激なpH変化に気づきやすくなるため、家庭での第一次確認として有効です。
高精度なガラス電極法・半導体センサーの活用
ガラス電極法は研究機関や大学の化学実験などで一般的に使われる測定法で、非常に精度が高いことが特徴です。家庭用としてはやや本格的な装置が必要になりますが、水耕栽培やこだわりの料理をする際など、正確なpH管理が求められるシーンで活躍します。また、最近では半導体センサーを利用した軽量コンパクトなpHメーターも登場しており、水回りでの取り扱いも比較的簡単です。
水道水のpHに異常が起きた場合の対策
通常は基準値内に収まるはずの水道水ですが、まれにpHが大きく変化するトラブルもあり得ます。
自治体や配管の設備不具合などが原因で水質に異常が出ることがあります。もし水に違和感のある臭いや色、味などが感じられた場合は、自治体や水道局の情報を確認することが第一です。家庭での応急処置としては、煮沸することである程度菌や不純物を抑えられますが、pH自体の調整までは難しい場合もあります。過去の事例を踏まえ、いざというときにミネラルウォーターやRO水を確保しておくなどの対策も検討すると安心です。ダイオーズが自社工場で製造するピュアウォーターは、RO(逆浸透)膜で塩素や不純物を徹底除去し、分子レベルまで磨き上げた文字通りの「純水」です。赤ちゃんから大人まで安心してお飲みいただけます。ダイオーズピュアウォーターの詳細はこちらから。
水道水で赤ちゃんのミルクを作る際の注意点について知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
過去に起きたpH異常事例とその解決策
かつては工場排水や設備老朽化によって、水道水のpHが基準値から外れる事故が報告されたことがあります。その際は地域住民への迅速な周知や一時的な飲用制限が行われ、原因を取り除きつつ浄水所のシステムを改修することで問題を解決しました。現在では監視体制がより強化されているものの、完全にリスクがゼロになるわけではありません。日常的にpH試験紙や自治体情報をチェックし、異常を早期に発見する姿勢が大切です。
まとめ:水道水のpHを正しく理解して安全で快適な水生活を
pHを知ることは、安全にそして美味しく水を使うための大切な第一歩です。
日本の水道水はpH5.8〜8.6という基準を守るべく管理されており、世界的にも評価が高い清潔な飲料水を日常的に享受できます。しかし、アルカリ性と酸性にはそれぞれの強みがあるため、用途や好みに合わせてpHを意識してみるのも一つの方法です。家庭でpHをはかる簡易的な方法も増えているので、料理や洗浄などで水の性質をうまく活かして、より充実した生活を送りましょう。